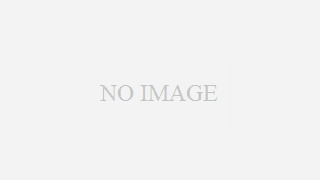EDの治療薬について
EDの治療薬について 過敏性腸症候群とED治療薬の関係について
過敏性腸症候群は、腸の機能が正常であるにも関わらず、慢性的な腹痛や腹部不快感、便通異常などの症状が現れる疾患です。この症候群はストレスや食生活の乱れ、過敏な腸の反応などが原因とされています。症状は個人によって異なり、軽度から重度までさまざまです。過敏性腸症候群は一般的に身体的な検査では異常が見つからず、診断は症状の経過や排除診断によって行われます。過敏性腸症候群は慢性的な症状を持つため、適切な治療が必要とされます。